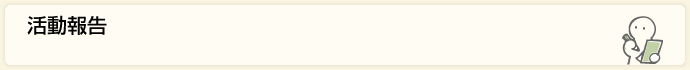ソフトウェア税務に関する法人税基本通達のお知らせ
根岸邦彦税理士(ACCS顧問)
2001年1月29日、国税庁よりソフトウェア税務に関連する法人税法基本通達が2000年11月29日付けで公表されましたので、その内容をご紹介します。
1. ソフトウェア税務関連の税法改正
ご承知のように、昨年(2000年)3月31日に下記のように法人税法の関連法規が改正され、ソフトウェアは無形固定資産として資産計上し、定額法の減価償却を行うことが規定されました。その趣旨は、
- 法人税法施行令第十三条(減価償却資産の範囲)に「ソフトウェア」が追加された。
- 法定耐用年数を規定する財務省令に、
- 複写して販売するための原本は3年(法定耐用年数表第3表)
- その他のものは5年(法定耐用年数省令第3表)
- 開発研究用に使用されるソフトウェアは3年(法定耐用年数表第8表)
の3つの資産が計上された。ということでした。
2. 本通達の内容
今回の対象通達は、改正1本追加6本です。さらに、旧来の購入ソフトウェアを繰延資産とする基本通達8-1-7が廃止されました。以下に通達の内容と、«解説»としてその意味をあげます。
通達とは、国税庁が、法律・政令・省令等の解釈や行政の運用方針について、下級庁に対して発する命令や指令であり、その性質は法律のように強制力を持つものではありません。法律が要求している以上の義務など納税者に課すものではなく、その解釈の参考となるべきものです。
1) まず棚卸資産の取得価格に関連する従来からの通達にソフトウェア資産の償却費の規定が追加されました。
(製造原価に算入しないことができる費用)
5-1-4 次に掲げるような費用の額は、製造原価に算入しないことができる。
(3)試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額は、製造原価に算入しないことができる。
(7)複写して販売するための原本となるソフトウェアの償却費の額
«解説»
この通達は昭和55年に制定され、従来この(3)によって新準の制定以前からパッケージソフトの開発費のうち、特定の製品に関連しない費用について、期間費用として処理する根拠となっていたものです。今回新たに(7)が新設されたので、ソフトウェア資産の償却費は原価ではなく期間費用として処理されることが明確になりました。なお、研究開発費に該当する部分の処理については、後記の7-3-15 の3に明確に規定されることになりました。
2)ソフトウェア資産計上に関連する通達
(研究開発のためのソフトウェア)
7-1-8の2 法人が、特定の研究開発にのみ使用するため取得又は制作をしたソフトウェア(研究開発のためのいわば材料となるものが明らかなものを除く。)であっても、当該ソフトウェアは減価償却資産に該当うることに留意する。
(注)当該ソフトウェアが耐用年数省令第2条第4号に規定する開発研究の用に供されている場合には、耐用年数省令別表第八に掲げる耐用年数が適用されることに留意する。
«解説»
研究開発費は、新基準により費用として処理されることが慣行となりましたが、その活動の中で使用されるソフトウェアについては、固定資産であることから、資産計上して減価償却を行い、その償却費が研究開発費とされるという確認的な規定です。
また、耐用年数表に突然登場した「開発研究用ソフト」の内容について、これを「開発ツール」(コンパイラやデバッガのようなもの)と、「組み込みモジュール」(ドライバやライブラリで、製品に組み込むことを目的に購入されたもの)に概念を分け、後者については材料費とする考えを示しています。
(自己の制作に係わるソフトウェアの取得価額等)
7-3-15の2 自己の制作に係わるソフトウェアの取得価額等については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウェアの制作のために要した原材料費、労務費及び経費の額ならびに当該ソフトウェアを事業の用に供するために要した費用の合計額となることに留意する。
この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。
(注)他の者から購入したソフトウェアについて、そのソフトウェアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業の費用の額は、当該ソフトウェアの取得価格に算入することに留意する。
«解説»
昨年の税法の改正の際には、無形固定資産に計上されるソフトウェア開発費の範囲が明らかでありませんでした。新基準によれば「マスター完成までの費用」は期間費用とされますが、税法ではこの通達にあるように法人税法施行令54条の規定で「原価すべて」が資産計 上の対象になるように読めたからです。
この通達は新基準や原価計算基準のような慣行の準用規定で、法人税法22条を確認したものです。この通達と次の通達により、上場企業など証券取引法の監査を受けている企業においては、資産計上される開発費について税法の扱いと会計基準上の扱いを統一 して行うことができると解釈されます。
注はインストール費の扱いです。
(ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用)
7-3-15の3 次にかかげるような費用の額は、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる。
(1)自己の制作に係わるソフトウェアの制作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係わる費用の額
(2)研究開発費の額(自社利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
(3)製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
«解説»
今回の通達では、この通達が一番重要であり、影響も大きいと考えられます。
(2)は、税務においてもソフトウェア開発費の中に研究開発に該当するものがあり、その費用は無形固定資産ではなく、期間費用として処理できる、とした規定です。これによりあいまいだった税法改正の解釈がはっきりしました。特に注目すべきは、対象となる支出が税法の用語である「試験研究費」ではなく「研究開発費」とされていることです。これは、この部分の解釈に新基準などの会計慣行を準用するこ とを意味していますので、税務と会計基準の整合性をはかることが可能になったわけです。
次に注目されるのは、(2)のカッコ書きで、これを逆読みすると「収益獲得・費用削減の見込める自社利用のソフトウェアは」無形固定資産への計上が強制される、という風に解釈できます。従来資産計上すべきだったのは、今回廃止された8-1-7による購入ソフトウェアだけでしたので、今後は財務会計や販売在庫管理といった社内利用のシステムを自社で開発した場合、その原価を計算して無形固定資産に 計上し、減価償却を行う必要があることが、税務の上でも明らかになったわけです。
(ソフトウェアの除却)
7-7-2の2 ソフトウェアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウェアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウェアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金に算入することができる。
(1)自社利用のソフトウェアについて、そのソフトウェアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウェアを利用することとなり、従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合。
(2)複写して販売するための原本となるソフトウェアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
«解説»
ソフトウェアは形が無いため、会計上の除却の処理が技術的に難しいことと、従来は繰延資産扱いであったため、「滅失」が除却の条件と解釈できなくもありませんでした。この通達は私共の業界の実状を詳細に説明した結果、従来から慣行的に行われてきた手続きを追 認していただいた意義があります。
(ソフトウェアに係わる資本的支出と修繕費)
7-8-6の2 法人が、その有するソフトウェアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。
(注)既に有しているソフトウェア、購入したパッケージソフトウェア等の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウェアを製作するための費用は、原則として取得価額となることに留意する。
«解説»
新基準で議論を呼んだのが、ソフトウェアのバージョンアップの費用の扱いでした。
新基準の「意見書」によると、会計基準の処理としては
イ) バグ取り等、機能維持の費用は発生時費用処理
ロ) 機能の改良・強化の費用は資産計上
ハ) 著しい改良の費用は研究開発なので費用処理
というものでした。これと比較すると、イとロは同じ、ハは逆の規定になっていることがわかります。従って、会計基準に従って財務諸表を作成する企業はこの点を税務申告調整する必要が生まれます。
しかしながら、製品の著しい改良の場合は新たな製品として扱う場合が多く、この場合には前述の原則的な処理が適用されますので、こ の矛盾が生じるケースは少ないと思われます。
旧来の(ソフトウエアの開発費用)8-1-7は削除されました。
«まとめ»
以上、基本通達の内容を俯瞰してみると、昨年の税法改正が基本的には税法と会計基準の整合性を確保するためのものであったことがわかります。従って、証券取引法の適用の無い一般のソフトウェア企業においても会計基準の規定や原価計算について十分に検討することが、ソフトウェア税務の処理にも必要になったということができます。
また、ソフトウェアユーザーである一般企業においても、ソフトウェアへの支出の会計処理に十分な留意が必要になったと言えます。特に大規模なソフトウェアを自社開発している金融業や流通業、ソフトウェアが重要な経営資源であるネット関連企業についても多大な影響があると思われます。
また、この通達には触れられなかったが、ゲームソフトのように法定耐用年数(3年)に比較して、実際の販売可能期間が著しく短いソフトウェアについては耐用年数の短縮の手続きが可能です。既にこの申請を行った企業もあると聞いております。
近日中に、これらの問題についてのセミナーを開催いたしますので是非ご参加ください。
«参考法令»
改正部分は以上ですが、これに関連して、改正されなかった法令の参照も必要です。
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
...(略)...
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
(減価償却資産の償却の方法) 法人税法施行令
第四十八条減価償却資産の償却限度額(法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この目から第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
四 第十三条 第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権及び第六号に掲げる営業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物定額法
(減価償却資産の取得価額) 同施行令
第五十四条減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。第六号イにおいて同じ。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二 自己の建設、製作又は製造(以下この条において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
(耐用年数の短縮)
第五十七条内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
一当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
....(略)...
- 年度を選択
- 2000(平成12)年度(3件)
- 2001(平成13)年度(5件)
- 2002(平成14)年度(9件)
- 2003(平成15)年度(11件)
- 2004(平成16)年度(15件)
- 2005(平成17)年度(14件)
- 2006(平成18)年度(14件)
- 2007(平成19)年度(42件)
- 2008(平成20)年度(37件)
- 2009(平成21)年度(34件)
- 2010(平成22)年度(29件)
- 2011(平成23)年度(19件)
- 2012(平成24)年度(28件)
- 2013(平成25)年度(28件)
- 2014(平成26)年度(32件)
- 2015(平成27)年度(29件)
- 2016(平成28)年度(14件)
- 2017(平成29)年度(6件)
- 2018(平成30)年度(9件)
- 2019(令和元)年度(12件)
- 2020(令和2)年度(9件)
- 2021(令和3)年度(8件)
- 2022(令和4)年度(17件)
- 2023(令和5)年度(7件)
- 2024(令和6)年度(31件)
- 2025(令和7)年度(1件)